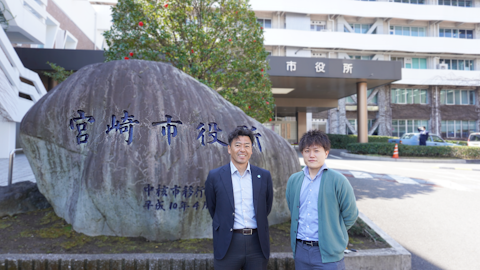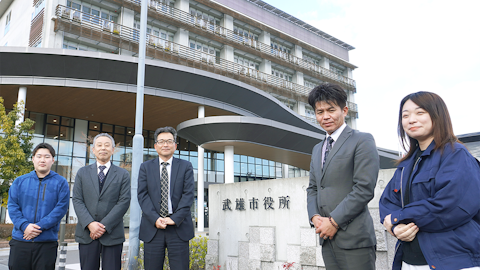ガブテック(Govtech)とは。行政デジタル化の最新事情
Govtech(ガブテック)とは、行政が民間企業のテクノロジーを活用して、電子申請やデジタル化などを進める取り組みを意味します。多くの自治体が、ベンチャー企業やスタートアップと連携することで、ガブテックの導入を進めています。
「行政×IT」によって、政府や役所の業務や働き方を変えていくガブテックは、2019年以降注目を集めています。2021年9月にはデジタル庁が設立、2022年6月にデジタル田園都市国家構想基本方針が決定し、デジタルの活用により「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」の実現が進んでいます。
この記事では、ガブテックとは何か、ガブテックのメリットをはじめ、ガブテック業界のイベントやセミナーなど、ガブテックの動向や事例について解説します。
更新日:2023年5月22日
Govtech(ガブテック)とは
Govtech(読み方は、ガブテック・ガヴテック。Gov Techとも記載する)とは、ガバメント・テクノロジーの略で、Government(行政)とTechnology(技術)を組み合わせた造語です。行政の業務にテクノロジーを取り入れることを意味します。非効率なアナログ業務に対して、デジタル技術を用いることで効率化していくのです。例えば、市民がスマートフォンから行政手続きを完結して、役所で長時間待つ必要がなくなるといったことも、ガブテックの一種です。

これまで日本の行政手続きの大半は対面で行われてきました。市民は手続きのために役所の窓口に並び、申請書類に何度も同じ情報を書くといった面倒な手続きに、多くの時間をかけてきました。混雑時には、数時間の待ち時間が発生することも珍しくありません。年間25億件を超える手続きのうち、オンラインで実施できる手続きは、種類ベースで全体の14%、件数ベースで全体の79%と言われています(※)。
(※)出典:内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室・総務省『行政手続等の棚卸結果等の概要』
このような状況に変化をもたらすのが、ガブテックです。テクノロジーを取り入れて自治体業務にデジタル技術を応用することで、オンラインで行える手続きが増え、市民の利便性は大きく向上し、自治体業務が効率化するのです。
ガブテックの具体的な取り組み
ガブテックの具体的な取り組みとして、「申請手続きのデジタル化」や「相談や問い合わせのデジタル化」、「窓口のデジタル化」などがあります。

1. 申請手続きのデジタル化
市民や事業者が行政に対して行う手続きをオンライン化する取り組みです。オンライン申請を導入することで、申請のために直接役所に出向く必要がなくなり、市民や事業者の手間が大幅に削減されます。
2. 窓口対応のデジタル化
窓口にかかわる業務をデジタル化する取り組みです。例えば、以下のような取り組みによって、窓口業務の一部をデジタルに置き換えることができます。
窓口の事前予約制の導入
グラファーが提供する「Graffer 窓口予約」等を利用することによって、窓口を事前予約制にすることができます。混雑の緩和や業務の平準化によって、「待たない窓口」「待たせない窓口」を実現し、市民サービスの向上につなげます。「書かない窓口」の導入
窓口での申請書作成をデジタル化することによって、「書かない窓口」を実現することができます。市民から情報を聞き取り、職員が申請書を作成するため「何枚も申請書に記入するのが大変」といった市民の手間を削減します。
3. 問い合わせ対応のデジタル化
問い合わせにかかわる業務をデジタル化する取り組みです。例えば、以下のように、問い合わせ対応にデジタルを取り入れることによって、職員の対応時間削減と市民の利便性向上を同時にかなえることができます。
電話対応のデジタル化
グラファーが提供する「Graffer Call」等を利用することによって、電話応答を自動化することができます。ホームページなどで解決できる問い合わせについては、SMSを自動送信することによって職員の電話対応時間を大幅に削減します。手続き案内のデジタル化
行政手続き数は多く、その中から自分に関連する手続きを探し出すのは大変です。グラファーが提供する「Graffer 手続きガイド」等を利用することで、スマホで質問に回答していくだけで、必要な行政手続きを絞り込むことができます。- チャットボットの導入
チャットボットとは、「対話(chat)」する「ロボット(bot)」という2つの言葉を組み合わせたもので、AI等の活用により問い合わせ対応を自動化する仕組みです
4. 情報発信のデジタル化
SNSやLINEを活用した情報発信を行う取り組みです。FacebookやTwitter、LINEの公式アカウントを活用することで、市民に対して、デジタルで効率的に情報を届けることができます。
5. 定型業務のデジタル化
大量の定型業務をデジタル化する取り組みです。AIやRPAなどのテクノロジーを業務に取り入れることで、大量の定型業務を機械に代替させたり、「kintone」などの業務システムを導入することによって、書類の処理をなくして運用を標準化します。定型の単純作業の時間を短縮して業務負荷を軽減する取り組みによって、業務の効率化や職員の長時間労働の削減効果が期待できます。
※RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略で、定型作業を自動化する手法を意味します。
ガブテックのメリット
ガブテックは市民、行政の双方にメリットがある取り組みです。
市民の利便性向上
ガブテックが導入されると、市民の利便性は高まります。これまで政府や行政では、多くの手続きがアナログで行われてきました。そのため市民の多くは「手続きが面倒だ」「税金に見合ったサービスがされていない」「民間ではオンラインが当たり前となっているのに」など、公共サービスに対して不満を感じていました。しかし、ガブテックが進み、手続きがネット上でできるようになったり、書面での手続きが必要なくなることによって、市民の利便性は大きく向上し、自由な時間が増えます。
行政の業務効率化
ガブテックの取り組みを進めることは、自治体の業務効率化にもつながります。自治体がデジタル技術を活用することによって、紙ベースで行われていた業務が、デジタルに置き換えられます。例えば、「紙で提出された申請書の内容を手作業でパソコンに入力する」といった業務が不要となったり、「書類の内容を目視でチェックして、誤りがあれば赤ペンで修正する」といったチェック業務が自動で行われるようになったりします。
業務の効率化に伴って、コスト削減や行政職員の働き方変革が進むといったメリットもあります。多くの自治体では、職員数が減少傾向にあるにも関わらず、市民からは安定的で質の高い行政サービスが求められています。テクノロジーを取り入れることは、人員の効率的な配置につながります。適切な職員配置が進むことで、長時間労働を削減しながら、本来力を入れたい業務に集中することが期待できます。
参照:内閣府『将来の公共サービスのあり方に関する世論調査』
参照:総務省『地方公共団体定員管理調査結果の概要』
ガブテックを後押しするベンチャーなどの民間企業
ガブテックを推進する際に注目されているのが、スタートアップ・ベンチャー企業です。たとえば神戸市では、2015年から民間企業と連携することで日本のガブテックをリードしています。また横浜市、鎌倉市、神戸市などの自治体では、ガブテックスタートアップであるグラファーと連携して、電子申請を押し進めています。
ベンチャーの持つテクノロジーの公共分野への活用については、政府による推進が進んでいます。2019年の統合イノベーション戦略推進会議では、日本国内のスタートアップ企業を倍増する計画が発表されています。公共調達における先進技術の導入や中小・ベンチャー企業の活用促進のための公共調達ガイドラインの策定も行われています。
参考:首相官邸『統合イノベーション戦略2019』
国内で進むガブテック事例
日本では、四條畷市などの自治体が先行して行政業務に積極的にデジタル技術を採用し、効率化を図っています。
1. 四條畷市の「住民票オンライン請求」
大阪府四條畷市では、2020年4月から住民がスマホで住民票を請求できる「住民票のインターネット請求」を開始しました。

住民は、スマホの申請画面で必要な通数や記載事項を入力して、マイナンバーカードで本人認証を行い、クレジットカードで支払いをするという流れで、住民票をオンラインで請求できます。申請書を印刷して記入したり、郵便局に定額小為替を買いに行ったりする手間と比較すると、圧倒的に簡単に請求できます。
2. 宝塚市の「お悔やみ窓口」へのデジタル活用
兵庫県宝塚市では、2021年1月から「お悔やみ窓口」へのデジタル活用を開始。

お悔やみ窓口とは、亡くなった住民のご遺族が、手続きをワンストップで行える窓口です。。亡くなった際の手続きは、福祉や税関連、相続に関するものなど多岐に渡り、ご遺族には大きな負担がかかります。そこで関連窓口への案内を一元化。ご遺族の負担を軽減します。
3. 行橋市の「窓口のオンライン予約」
福岡県行橋市では、確定申告に関する窓口相談の予約をオンライン化しています。
以前は、電話と窓口で予約を受け付けて、紙の受付簿で管理していたため大きな負担がかかっていました。しかし、スマートフォンで予約・変更・キャンセルなどの操作が行えるようになったことで、職員の事務負担は半減しています。
4. 神戸市の「新型コロナ関連補助金申請オンライン手続き」
兵庫県神戸市では、新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業への迅速な支援が求められる中、市が独自に制定した補助金の申請受付に、オンライン申請を活用しました。
 実際に「中小企業チャレンジ支援補助金」では申請全体の8割がオンラインで提出され、オンライン申請が広く活用されました。
実際に「中小企業チャレンジ支援補助金」では申請全体の8割がオンラインで提出され、オンライン申請が広く活用されました。
5. 広島市の「被災者支援ナビ」
広島県広島市では、被災者がスマートフォンで公的支援をリストアップできる「被災者支援ナビ」を活用しています。
被災者は、スマートフォンで質問に回答していくだけで被災状況に応じて、受けられる支援をリストアップすることができます。これまで大規模な災害が発生した時に被災者は、窓口に相談しながら、自分に必要な支援策を確認する必要がありました。しかしスマートフォンから支援策が確認できるようになることで、役所に行かなくても簡単に確認できるようになりました。
6. 呉市の「放課後児童会のオンライン申請」
広島県呉市では、放課後児童会(学童保育)の申し込みにオンライン申請を活用しています。

「忙しい親に何度も訪問させたくない」という思いから、放課後児童会の申し込みをデジタル化した呉市。保護者はこれまで手続きのために、多い場合で3回、児童会に足を運ぶ必要がありました。しかし、オンライン申請を導入したことによって、訪問回数は個別面接時の1回に減少。オンライン申請の利用率は約97.1%と非常に高く、多くの保護者に利用されています。
ガブテック関連のセミナーやイベントも定期開催
国内では2019年を皮切りに、ガブテック関連のイベントやセミナーなどが開催され、国内のガブテックを後押ししています。
グラファー「デジタル化説明会」
株式会社グラファーでは、新しくデジタル行政推進を担う方や、手続きのデジタル化をお考えの窓口担当課の方向けに「デジタル化説明会」を定期開催。国の動向や自治体の行政デジタル化の手法などについて紹介しています。
デジタル庁「GovtechMeetup」
行政デジタル化の知見の共有と交流を目的にデジタル庁が開催している「GovtechMeetup」。日本のデジタル化のあるべき姿が、デジタル庁の観点から紹介されています。デジタル庁のTwitterでは、GovtechMeetup以外のイベントや取り組みについても取り上げられています。
経済産業省「Govtech Conference Japan」
経済産業省をはじめとした中央省庁のDX、Govtechの事例を紹介する「Govtech Conference Japan」。定期的に開催されており、国内のガブテックの動向や新しいテクノロジーなどの事例を知ることができます。
神戸市「GovTech Summit」
神戸市では定期的に「GovTech Summit(ガブテックサミット)」を開催しています。神戸市は2019年を「ガブテック元年」と位置付け、自治体目線から先進的な取り組みを発信しています。
デジタルガバメントラボ
自治体出身者が集い、自治体におけるデジタルガバメントの実現を目指して活動するデジタルガバメントラボ。活動を通じて得たノウハウや研究成果の横展開を進めています。イベントを定期的に開催しており、Facebookページで最新情報が入手できます。
日本のGovtechは今後さらに拡大していく
ガブテックとは何か、どんなメリットがあるのかを解説しました。
労働人口の減少や行政の財政問題などの課題を背景に、その解決策の1つであるガブテックは、今後さらに国を挙げて推進されていくことが予想されます。2019年5月には行政機関に手続きのオンライン化を義務づける「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)」が施行。2020年1月に始まったコロナ禍でデジタル化の遅れに起因する課題が浮き彫りになったことも相まって、2021年5月にデジタル社会形成基本法を中核としたデジタル改革関連6法が成立し、同年9月に司令塔となるデジタル庁が設置されました。このような流れを受けて、経済の持続的な発展や、国民の幸福な生活の実現等に向けたデジタル社会の形成が大きく進んでいくことになります。
一方で、日本の自治体の手続きにはまだ紙や手作業によるものが多く、それらをデジタルに置き換えるためには、制度面や運用面で多くの変更が必要になるといった課題もあります。デジタルに置き換えるためには費用も手間もかかるためです。しかし、労働力不足が深刻化することが予想される社会で、行政手続きだけが非効率なまま続くことは難しいと考えられます。今後、各自治体でのより具体的な対策が期待されます。

「プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える」をミッションに掲げ、市民と行政職員の利便性を追求したデジタル行政プラットフォームを提供するスタートアップ企業であるグラファーでは、各自治体のデジタル変革を後押しするサービスを提供しています。
あらゆる行政手続きをオンラインで完結する「Graffer スマート申請」、簡単な質問に答えるだけで行政手続きを洗い出せる「Graffer 手続きガイド」、カンタン予約で「待たない窓口」を実現する「Graffer 窓口予約」、孤独・孤立対策に役立つ「お悩みハンドブック」を活用することによって、デジタル化を推進します。
製品の導入期間や費用については、お問い合わせ窓口からお気軽にご相談ください。
グラファー Govtech Trends編集部
Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。
株式会社グラファー
Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『Digital Government for the People』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。