人口:
24.26万人(令和2年国勢調査)
導入サービス:
Graffer スマート申請
Graffer 手続きガイド
Graffer Call
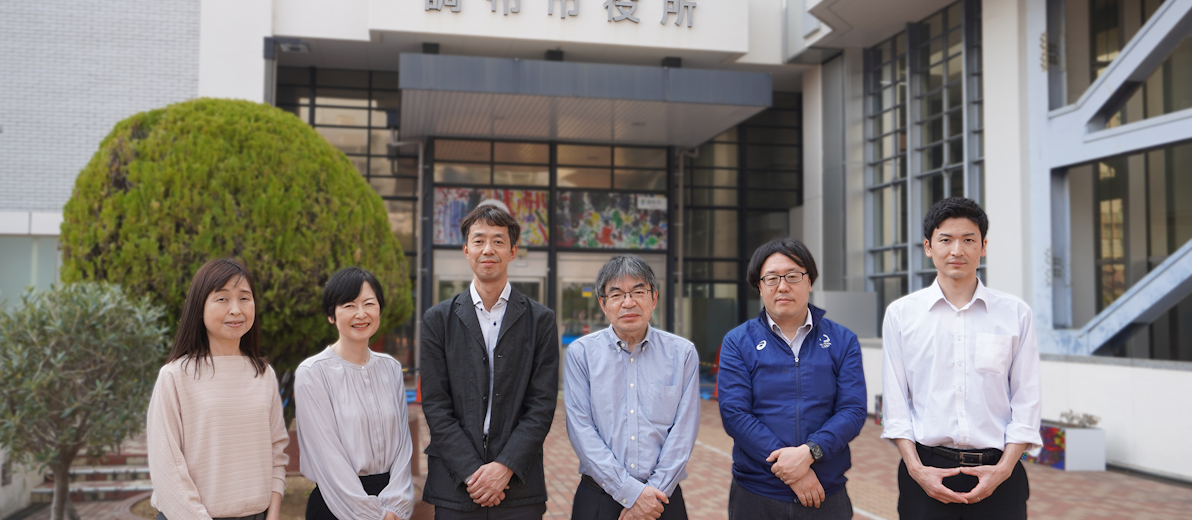
東京都調布市の保険年金課では、問い合わせ業務に「Graffer Call」のIVRを活用。マイナ保険証などに関する問い合わせが集中し、電話がつながりにくくなる状況に対して市民が抱く不安の解消に取り組んでいます。よくある疑問についても、電話での自動アナウンスや市HPへの案内を行うことによって、市民がスムーズに用件を済ますことができる仕組みを整備しました。
※IVRとは
自動音声によって電話応答を行い、問い合わせ内容に応じた案内を自動で提供する仕組みです。
国民健康保険などに関する市民からの問い合わせへの応対にIVRを活用しています。市民が担当課に電話をかけると自動音声が流れ、案内に沿って該当する番号を押していくことで、適切な情報にアクセスできる仕組みです。

市民は自動音声に従って用件を選択する。
大阪府吹田市の国民健康保険課が「Graffer Call」を活用して、電話業務の見直しに成功した事例を見たのがきっかけです。
保険年金課ではこれまで、問い合わせが集中するとすべての電話回線がふさがってしまい、市民が不安や不満を感じるという状況を課題に感じてきました。例えば、通知の発送直後や、メディアでマイナ保険証が取り上げられたタイミングには、問い合わせが特に集中していました。職員の事務の観点では「受話器を置くとすぐに次の電話が鳴り、事務がまったく進まない」という状況が発生していました。このような課題を何とかできないかと考え、「Graffer Call」の導入を検討し始めました。
 福祉健康部 保険年金課 給付係 宮﨑 房子氏
福祉健康部 保険年金課 給付係 宮﨑 房子氏
「Graffer Call」は同時に多くの電話を受けられるため、電話をかけたすべての方に対して、混雑状況によらず自動案内できる点を評価しました。また、アナウンスを通じて市民が疑問を自己解決できるように工夫できる点にもメリットを感じました。例えば3月や4月は就職などで保険の切り替えが発生するため、加入・資格喪失手続きに関する同じような問い合わせが集中します。こうした問い合わせに対して、電話の混雑時や閉庁時にもスムーズに案内できる仕組みを構築することが、市民サービスの向上につながると考え、導入を決めました。
導入時には、「デジタル田園都市国家構想交付金(現「新しい地方経済・生活環境創生交付金」)」を活用しました。事業推進体制にサービス提供事業者を巻き込み計画作成段階から一緒に考えることができたため、申請に必要な実施計画の作成もスムーズに進められました。
 導入にはデジ田を活用した。
導入にはデジ田を活用した。
一つ目のメリットは、電話が集中している際に「ツーツーツー」という音だけが流れて、何が起きているのか分からないという状況を解消できた点です。混雑時には「順番におつなぎしています」というアナウンスが流れるようになり、市民は状況を把握しやすくなりました。その結果、不安や不満の声を耳にすることはほとんどなくなりました。
二つ目のメリットは、市民が職員と会話しなくても、自動音声だけで用件を完結できる場面が増えたことです。自動音声やSMSを通じて解決できる疑問については、職員につなぐまでもなく解決できるため、市民はよりストレスなく、短時間で疑問を解消できるようになりました。
三つ目のメリットは、電話の件数を定量的に把握できるようになったことです。以前は、どれだけ電話がかかってきているのかが分からない状況でしたが、「Graffer Call」ではログを簡単に確認できるため、業務の見直しや改善に役立てることができます。

自動音声やSMSにより市民サービスと職員の利便性の向上を実現した。
自動音声に対する市民からの苦情は特に寄せられていません。導入前には自動音声に対して苦情が入るのではないかという懸念がありましたが、実際にはそのような声は届いておらず安心しています。
電話での自動音声のアナウンスを工夫しました。例えば、マイナ保険証への切り替えタイミングでは、問い合わせが殺到するのではないかと想定していました。そこでアナウンスの冒頭にマイナ保険証に関する文言を入れて、スムーズに案内できるようにしました。

市民が迷いやすそうな内容は、アナウンスを工夫して解決に取り組んだ。
他にも、問い合わせが増えそうな時期には、申請フォームのURLをSMSで送付するようなフローを加えています。自動音声だけで不明点が解決する方については、アナウンスの最後に「要件がお済みの方は電話をお切りください」という案内を入れることで、市民が迷わないような工夫をしています。
アナウンスを切り替えるときは、まずは担当の職員が原案を考えてテスト用の電話番号に設定を行い、庁内での決裁を取ります。切り替えのタイミングでは、電話番号の紐付けを変更するだけで、市民への公開用に変更することができるため非常にスムーズに行えます。
「Graffer Call」の導入をきっかけに、市民の利便性をさらに向上させる方法を検討する機会が増えています。例えば、「電話をしなくてもよいように、オンライン申請を拡充できないか」「電話以外の方法で市民が疑問を解消できるようにしたい」などのアイディアが浮かびやすくなってきているように感じます。グラファーのアドバイスも受けながら、今後も市民の利便性向上と職員の業務負荷軽減を両立できる取り組みを進めてまいります。
取材・写真:柏野幸大 / 取材・文:東 真希(Govtech Trends編集部)
(※文中の敬称略。撮影時のみマスクを外しています。所属や氏名、インタビュー内容は取材当時のものです。)
Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。
株式会社グラファー
Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。
人口:
24.26万人(令和2年国勢調査)
導入サービス:
Graffer スマート申請
Graffer 手続きガイド
Graffer Call