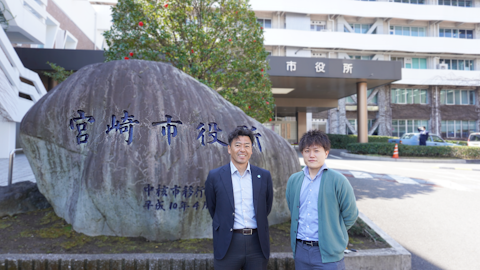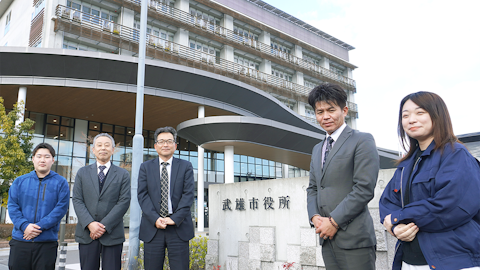見直し完了率93%。なぜ福岡市は「アナログ規制の見直し」を全国に先駆けて実現できたのか
令和3年から全国に先駆けてアナログ規制の見直しに取り組んできた福岡県福岡市。その見直し完了率は93%に達し、全国でもトップクラスの進捗率です。福岡市ではどのようにして見直しを進めているのでしょうか。これから取り組みを進める自治体にとって参考になるスケジュールや体制について伺いました。
アナログ規制の見直しとは
アナログ規制の見直しとは、従来の「対面」や「目視」などを前提とした規制を、デジタル技術の活用を前提とした形に改める取り組みです。2021年から国が主導して改正を進めた結果、対象の約96%の見直しが完了したことが発表されています。一方、自治体独自の条例や規則に基づく規制については、今後、自治体ごとの取り組みが求められています。
参考記事:一番やさしい「アナログ規制見直しの基本」自治体の6つの疑問に回答
1. 全体的なスケジュール
——福岡市では全国に先駆けてアナログ規制の見直しを進めています。まず、取り組み全体のスケジュールについて教えてください。
吉原:令和3年11月に福岡市の高島市長がデジタル臨時行政調査会の構成員に就任したことをきっかけに、アナログ規制見直しの取り組みについて検討をスタートしました。
令和4年2月には対象条例等の一覧を作成。その後、所管部署との調整を経て改正に着手し、令和4年6月および令和5年9月に条例等の改正を実施しました。令和6年12月時点では、改正を必要とした条例等のうち93%の見直しが完了しています。

福岡市では令和4年、5年にアナログ規制見直しのために条例等の改正を実施した。
——令和4年6月、令和5年9月に実施した条例改正について、それぞれどのような内容だったのか教えてください。
吉原:令和4年6月には、国のアナログ規制7項目にある「目視規制」や「往訪閲覧・縦覧規制」などにあたるいくつかの条例を改正しました。

代表的なアナログ規制は、大きく7項目に分類できる。
例えば、映画館や野球場など興行場の定期清掃については、これまで1日に1回以上の清掃や、1カ月に1回以上の消毒といった定期的な対応を義務づけていましたが、利用状況や汚れの度合いに基づく清掃・消毒を可能として、定期的な対応を廃止しました。また、飼い主不明の犬の公示についても、インターネットでの公示を可能にするなどの改正を行いました。

令和4年6月、令和5年9月に行った条例改正。
令和5年9月には「書面掲示規制」に関わる条例を一括で見直し、これまで特定の場所に書面で掲示が必要だった情報を、インターネット上でも閲覧できるよう義務付けました。例えば、市役所内の自転車駐車場が休場する際の掲示を、オンラインでも閲覧することを義務付ける改正を行いました。

市役所内の自転車駐輪場の様子。従来は、休場する際は写真のような現地の看板のみだったが、オンラインでも休場が確認できるようになった。
2. 推進体制
——見直しにあたって、どのような推進体制を取ったのでしょうか。
吉原:福岡市では、法制担当、行革担当、DX推進担当の3部門からそれぞれ2名ずつ、計6名をメンバーとしたプロジェクトチームを立ち上げ、令和4年4月には、新たに設置した「総務企画局DX戦略部サービスデザイン担当」に推進業務を移管しました。
また、DXの取り組みについて全体的なガバナンスを強化するため、副市長をCIO(Chief Information Officer)とした、局長級が参加する「DX推進会議」を設立。プロジェクトチームや所管部署だけで進めるのではなく、幹部会議を通じた報告体制を構築し、アナログ規制見直しの取り組みについても理解を求めることで、トップダウンと現場の意見を融合した推進体制を構築しました。

プロジェクトチームによる推進と並行して、幹部会議で合意を取りながら取り組みを進めた。
——もともとのきっかけは、市長がデジタル臨時行政調査会の構成員に就任したことでしたが、それだけではなく、推進体制にもさまざまな工夫が見られますね。
吉原:トップダウンのみでは、やはり現場に取り組みを浸透させるのは難しい部分もあります。取り組みの意義や考え方を現場の職員一人ひとりに理解してもらうためには、全庁的な合意形成が欠かせないと考えています。

総務企画局 DX戦略担当 課長 吉原 瑛二氏
——取り組みの開始後には進捗状況の把握も重要になってくるかと思います。どのように把握しましたか。
吉原:所管部署に対して対象リストをもとに全庁照会を実施し、情報を更新しながら進捗状況を把握していました。この対象リストは「見直し予定時期」だけでなく、「見直しが難しい場合の理由」なども記載しており、所管部署との調整状況は「DX推進会議」を通じて全庁に共有しました。令和6年3月に対象リストの内容をもとに、福岡市独自の工程表を作成し、見直しを進めるよう方針決定しました。また、工程表はその後も定期的に更新し、進捗の遅れがある場合には、該当する課に対して確認を行い、適宜フォローアップを実施しました。
新飼:対象リストや工程表の活用によって、全庁的な視点で進捗状況を「見える化」できるようになりました。状況が一目で把握できるようになった結果、庁内全体での進捗管理がスムーズに進むようになったように思います。また、現時点で見直しが難しい項目があっても、工程表等を活用することで、将来的な対応を迅速かつ効率的に行える基盤を整備できたと考えています。

工程表等を通じて、進捗状況を適切に確認しながら進めた。
3. 見直し対象条例の洗い出しの方法
——見直し対象条例の洗い出しについては、どのように進められたのでしょうか?
新飼:まず、令和4年2月に法制担当が見直し対象となる条例の一覧を作成しました。具体的には、「目視」「検査」「常駐」「掲示」など、アナログ規制に関連するキーワードを例規システムに入力して対象となる条例を洗い出しました。その後、行革担当がこの一覧を精査し、重複している項目やアナログ規制に該当しない項目を除外しました。さらに、全庁に点検依頼を行い、所管部署に内容を確認・補足してもらう形で最終的なリストを完成させました。
——それぞれの工程にはどのくらいの期間がかかりましたか?
新飼:法制部門による洗い出し、一覧化に約1週間、行革担当による精査に約1週間、全庁点検及び確認に約4週間を要しました。全体で約2カ月で作業を完了しています。

見直し対象条例の洗い出し及び確認は計2カ月で進めた。
——もっと長い期間がかかると想定している自治体もいるのではないかと思いますが、想像よりも短期間で洗い出しを行ったのですね。
吉原:そうですね。現在であれば、デジタル庁が提供するマニュアルや参考資料、先行自治体の実例も充実しているので、さらに効率的に進められるのではないかと思います。
4. 代替技術の探し方
——アナログ規制の見直し後、その代替技術はどのように探しましたか?
新飼:まず、所管部署に対して「アナログ規制をデジタル化するために適した代替技術があるかどうか」をヒアリングしました。その際は、導入済みの製品やサービスを中心に、代替技術として活用できるものがないかを確認しました。
——プロジェクトチームが代替技術を提示するのではなく、所管部署に発案してもらったということですね。
吉原:はい、国が提示している「アナログ規制7項目」も参考にしながら、所管部署の職員に現場の実情に合った代替技術も検討してもらいました。
——代替技術の検討については今後も同様に進めていきますか。
新飼:今後は、デジタル庁が提供する「技術カタログ」や「テクノロジーマップ」の活用にも期待しています。これらの資料には、さまざまな行政業務に活用できるデジタル技術やツールが一覧化されており、所管部署の職員が効率的に適切な技術を検討できることを期待しています。

出典:「アナログ規制見直しに活用できるテクノロジーマップ・技術カタログに関する取組」
5. 所管部署とのコミュニケーション
——これから見直しを始める自治体にとって、所管部署の巻き込みは重要な要素だと考えています。一部では後ろ向きな反応も想定されますが、コミュニケーションにおいて意識した点はありますか。
新飼:確かに、所管部署からは「現行の運用でも特に問題ない」「ルールを変更すると市民や事業者に影響が出るのでは」といった意見が寄せられることもありました。こうした不安や懸念を解消するために、「なぜこの見直しが必要なのか」という背景や目的を丁寧に説明することを重視しました。
——具体的なコミュニケーションの中で、特に意識したことはありますか。
江副:所管部署に直接出向き、丁寧に話を聞く姿勢を意識しました。特に、市民や事業者に影響を及ぼすような内容については、担当者が慎重になるのは当然のことです。そのため、「なぜ現在のやり方を採用しているのか」「なぜ見直しが困難だと考えているのか」を具体的にヒアリングしました。また、現場での実際の運用を見せてもらいながら、課題や制約を共有し、一緒に解決策を考える姿勢を大切にしました。

総務企画局 DX戦略部 DX戦略課 DX戦略係長 江副 可那氏
——一方的なコミュニケーションではなく、伴走型の支援を意識したのですね。
吉原:はい。所管部署との調整では、無理に見直しを押しつけるのではなく、現場の職員が納得した形で進めることを心がけました。現場を最もよく理解しているのは所管部署の職員自身です。そのため、彼らの意見を尊重し、課題に対する解決策をともに考える姿勢が重要です。このように、現場の意見を反映させた形で見直しを進めることで、職員の理解と協力を得ることができたのではないかと考えています。
6. これから取り組む自治体へのメッセージ
——これから見直しに取り組む自治体へのアドバイスをお願いします。
新飼:市民の利便性を向上させたり、業務を効率化させたりしたいという思いは、どの担当者にも共通してあるはずです。その思いを所管部署の職員と共有し、一緒に課題を解決していく姿勢が、最終的に、前向きな推進につながるのではないかと思います。

総務企画局 DX戦略部 DX戦略課 DX戦略係 新飼 夏実氏
江副:福岡市では93%の見直しが完了していますが、これはあくまでスタートラインです。本当に重要なのは、見直しをきっかけにテクノロジーを活用し、市民サービスや行政職員の業務をいかに便利にするかという観点を持つことです。テクノロジーは日々進歩していきますので、見直しが完了した後も、社会の変化や技術の進展に応じて、常に情報を収集し、継続的な改善を重ねていくことが必要だと考えています。
吉原:アナログ規制の見直しは、全国の自治体にとって手間のかかる取り組みの一つだと思います。しかし、現在ではデジタル庁から多くの情報や支援が提供されているため、国や他自治体と連携しながら進めることによって、より効率的に取り組みを進めることができるようになってきているように思います。また、最終的には住民や職員にとっての利便性向上や業務削減を大きく後押しするものです。ぜひ一緒に取り組みを進めていきましょう。
アナログ規制の見直しに関する解説は以下の記事でご覧いただけます。ぜひ庁内のデジタル化にお役立てください。
グラファー Govtech Trends編集部
Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。
株式会社グラファー
Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。