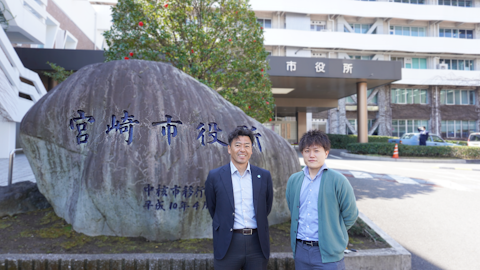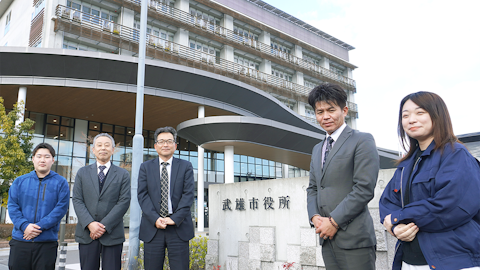デンマーク行政職員インタビュー【政府ICT管理課】「イノベーションよりも今あるシステムをちゃんと使う」「デジタル化で女性をエンパワーメントする」と語る背景とは?
ICT先進国として常に世界の先頭を走ってきたデンマーク。デンマークの電子政府の成功には、ユーザーファーストのコンセプトがあると言われています。
デンマークの行政デジタル化に長年携わってきたKaren Ejersbo Iversen(カレン・エイェルスボ・ルベルセン)氏は、行政サービスのデジタル化で日本の社会がどのように変わるのか、強く関心を寄せています。
行政サービスのデジタル化で、市民にもっとメリットを感じてもらうためには、どうしたらいいのでしょうか。カレン氏にお話しを伺いました。
カレン・エイェルスボ・ルベルセン氏
デンマーク政府ICT管理課 マネジメント チーフアドバイザー。1988年からデンマークの財務省などに勤務し、そのうち約20年間は主に行政のデジタル化に従事。2020〜2021年には、在日デンマーク大使館でデジタル化のシニアエキスパートとして勤務。

ニューハウン港 コペンハーゲン中心部
デンマークの電子政府、その成功の理由は
——デンマークでは、市民はどのような流れで行政手続きを行うのでしょうか。
市民は、市民ポータルにアクセスして行政手続きを行います。国・地方自治体全ての手続きの窓口が、この市民ポータルに集約されています。デジタル個人IDでログインしてポータルに入り、必要な手続きを行うことができます。ただ実際には、ほとんどの手続きはプッシュ型で完了してしまうので、市民は何もする必要がありません。
——デンマークで最初に電子政府戦略が策定されたのは、日本とちょうど同じ2001年と聞きました。なぜデンマークではこのようにスムーズに行政のデジタル化を進めることができたのでしょうか。
実は、デンマークで個人番号が導入されたのは1968年と、デンマーク政府が行政のデジタル化に取り組み始めるかなり前のことでした。かなり前から個人番号によってすでに国民の情報が整理されていました。
また、80年代に経済危機的な状況に陥った際、福祉社会を守るために、近代化の戦略として行政のデジタル化に取り組んできたという背景もあります。行政を効率化して人手をできるだけ介護などの分野に集中しようというアイディアだったのですが、当時、社会党から保守党まで、政党に関係なく皆がそれに合意しました。
デンマークの人口は、現在580万人ほど。 中央政府の下に5つの地域(Region)、その配下に98市町村(Kommune)が設置され、基礎自治体であるKommuneを中心に住民サービスが提供されています。
デンマークはそれほど大きな国ではないため、資金が潤沢にあるわけではありません。また、デンマークの銀行は、隣国であるドイツなどの大規模な銀行との競争にさらされており、効率的かつ合理的に運営する必要がありました。こうした背景のもと、デンマークでは銀行が連携し、共通のデジタル個人IDを作ることができました。さらに、国、地域、市町村が協力して、市民ポータルなどのデジタル公共サービスの仕組みを整備してきたのです。

デンマークでは、2001年に策定された電子政府戦略に基づいて、中央政府のみならず、地方自治体を含めたあらゆる行政機構の協働により、行政システム全体の最適化が推進されている。
ユーザーの視点を大切に
——そのような背景があってデジタル化が大きく進んでいるのですね。市民にとっては手続きがポータルで一元化されているのは、やはり分かりやすくてメリットが大きいですね。
そうですね。例えば、引越しをするとき、行政手続きだけではなく、電気・新聞とか色々な手続きが発生しますよね。市民にとっては、公的機関なのか、民間なのかは関係ないですから、とにかく市民の目線で分かりやすいように、安心して手続きを完了できるように、使いやすいUXになるように徹底的に議論をしています。
市民向けデジタル行政サービスの開発には「参加型デザイン」という手法が使われており、実際に色々な方に参加してもらって、ユーザーテストを行っています。
(※1)参加型デザイン:ユーザーがさまざまなステークホルダーとともに、技術開発や評価などのデザイン・プロセスに能動的に関与することで、システムの仕様やデザインを決定するアプローチ。
——他に、デンマークや日本での経験から「日本のデジタル化を進めるうえでも役に立つのではないか」と思うようなポイントはありますか?
そうですね、ひとつは「ユーザーの視点でシステムを設計する」というポイントです。皆が分かっているはずのことですが、開発した後に、「これでは使えない」ということが、実際に時々起こっています。ひとつの例ですが、いくつかの部門が一緒に使うシステムを作るときに、部門間の調整が不十分で、結果的にある部門にとっては使えないものが開発されてしまうということがあります。最初から全てのユーザーの視点に立って、システムを設計するということは、とても大切です。
もうひとつは「イノベーションよりも今あるシステムをちゃんと使う」という点です。デンマークの大きな自治体や省庁では、利用中のシステムが300〜500あり、システムによっては、適切に理解されていない、あるいは適切に使われていないといった状況もあります。これまでは、どちらかというと「新しいテクノロジー」や「新規システムの開発」の方に重きが置かれていましたが、これからは「今あるシステムのメンテナンス」の方が大切だと考えられていると感じます。
——なるほど、イノベーションよりも今あるシステムの管理や活用を重視するような風潮になっているのは、とても興味深いですね。
デンマークでは、国が新しい主要なITプロジェクトを始めようとするときには、必ず独立したICT審議会において、詳細な審査を受けなければならないことになっています。そして、プロジェクトが始まった後は、年に2回、進捗状況を政府に報告し、予算に変更があるかどうかを報告しなければなりません。
以前は、新しいシステムの開発に優先してお金が使われる傾向がありました。しかし最近は今あるシステムの管理や活用が重視されているので、例えば、ある省庁で新しいシステムを開発しようとしたときに、すでに別の省庁で開発されたものがあれば、それを使えばいいじゃないかと考えるようになっています。
行政のデジタル化による女性のエンパワーメントとは
——次にカレンさん自身についても聞かせてください。カレンさんは日本の行政のデジタル化の研究も行われているということですが、どのようなテーマの研究なのですか?
日本で、市民に対する行政サービスのデジタル化が進められていく中で、デンマークや日本での経験を活かして何か役立つような研究がしたいと考え、昨年からは「デジタル化でどのように日本の女性をエンパワーメントすることができるのか?」というテーマで研究を始めています。
——「デジタル化で女性をエンパワーメントする」というのは、とても興味深いテーマです。具体的にはどのようなイメージをお持ちなのでしょうか。
日本では、ジェンダーギャップがとても大きく、さまざまな課題がありますよね。例えば、市区町村長の女性の割合は、たった3.6%です。これは、自治体の将来のデジタル化に対して女性の影響力が非常に小さいということを意味しています。
日本の女性は、世界的にみても非常に睡眠時間が短いという記事を読んだこともあります。共働きの夫婦が80%以上ですので、子どもが生まれた後、睡眠不足が深刻になっているという話も聞いています。
「時間の貧困」という言葉がありますが、行政のデジタル化で手続きなどの効率性が向上することで、市民に少し自由な時間を与えられるという意味で、まさに時間の貧困の状態にある日本の女性に力を与えることができるのでは、と考えています。
また「行政の透明性」も重要なひとつのポイントです。デンマークでは、税金や年金の支払い状況や、何か申請したときにその申請の処理がどこまで進んでいるかなどを、市民ポータルサイトにログインして確認できるようになっています。行政は個人に対して力を持っているので、行政のデジタル化によって透明性を高めることにより、個人に力を与えることができると考えています。
——当社のサービスも、妊娠・出産、子育ての分野では、利用者となる市民の方の年代が比較的若いため、オンラインに対する抵抗感が少なく、利用率も高くなる傾向があるように感じます。
そうですね。私も日本で、複数の妊娠中の女性に話を聞いてきましたが、彼らは、本当にデジタルに慣れているので、行政手続きがもっとオンラインでできればいいのに!と感じることが多いようでした。今後、日本の行政手続きオンライン化が加速することで、彼女たちがもっと便利に感じられるようになることを期待しています。
——大変貴重なお話をありがとうございました!

デンマーク政府ICT管理課 マネジメント チーフアドバイザー Karen Ejersbo Iversen(カレン・エイェルスボ・ルベルセン)氏
グラファー Govtech Trends編集部
Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。
株式会社グラファー
Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。