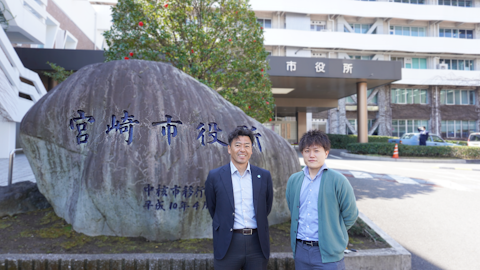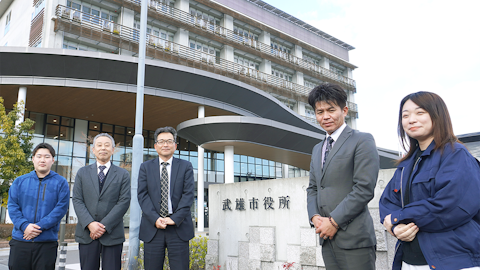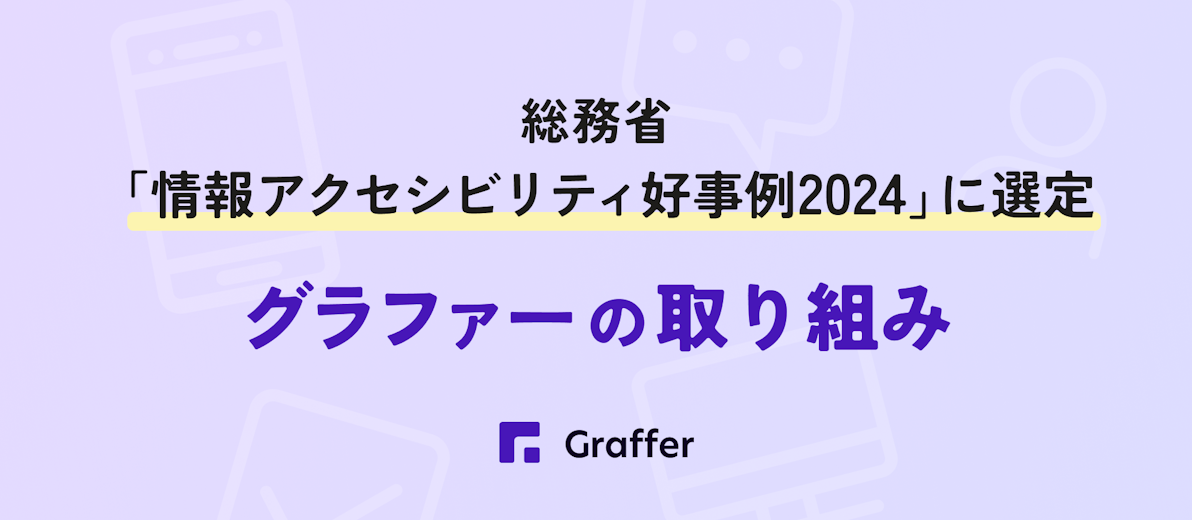
ウェブアクセシビリティに関するグラファーの取り組み 〜総務省「情報アクセシビリティ好事例2024」に選定 〜
誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向けて、一つの重要な観点となるウェブアクセシビリティ。グラファーでは、ウェブアクセシビリティの向上に向けて、取り組みを進めています。直近では、2025年3月に総務省が行う「情報アクセシビリティ好事例2024」に選定。アクセシビリティに対応するためにどのような取り組みを進めているのか、取り組みを支えるメンバーの声とともにお届けします。
総務省「情報アクセシビリティ好事例2024」に選定
——2025年3月に、「Graffer スマート申請」が総務省「情報アクセシビリティ好事例」に選定されました。どのような取り組みが評価されたのでしょうか。
評価を受けた一つ目のポイントは、幅広い方にとって使いやすい機能と画面設計です。「Graffer スマート申請」では、様々な障害を持つ方がスムーズにオンライン申請を行えるよう、音声読み上げの挙動や文字の色・大きさなど、アクセシビリティに配慮した設計が取り入れられており、障害の有無にかかわらず、多くの利用者にとって使いやすいサービスを提供することを目指しています。
二つ目のポイントは、アクセシビリティを推進するための組織的な取り組みです。グラファーでは、デザインエンジニアチームが中心となり、社内横断的にアクセシビリティを推進しています。具体的には、デザインエンジニアチームによるレビューを行う仕組みを構築し、アクセシビリティの向上を日常的な開発プロセスの一部として実践しています。このような体制が、アクセシビリティの継続的な改善を可能にしています。
 グラファーが情報アクセシビリティ好事例2024に選定された
グラファーが情報アクセシビリティ好事例2024に選定された
——開発プロセスの中にアクセシビリティが組み込まれているのですね。取り組みのきっかけは何だったのでしょうか。
自治体職員からの声が大きなきっかけとなりました。行政手続きは日本で生活する上で欠かせないものですが、障害者や高齢者、デジタル機器に不慣れな方々にとって、オンライン申請は壁となる場合があります。こうした課題を受けて、グラファーでは「誰もが使いやすい申請サービス」を目指し、アクセシビリティ向上に本格的に取り組むようになりました。
デザインシステムやウェブアクセシビリティ方針の公開を通じたアクセシビリティ向上への取り組み
——どのような取り組みからスタートしたのでしょうか。
まずは、プロダクト全体を通じたガイドラインである「デザインシステム」を、アクセシビリティを考慮した形に改修しました。デザインシステムを通じて、プロダクト全体に統一感のあるアクセシビリティ基準を適用し、どの機能や画面でも一貫して使いやすく、誰にとっても利便性の高い設計を実現しています。
——デザインシステムへの対応の後は、どのような取り組みを行いましたか。
2023年8月には「Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針」を公開しました。ウェブアクセシビリティ方針とは、企業がアクセシビリティに対してどのように取り組んでいるかを示し、その試験結果をまとめたものです。グラファーでは、国際基準であるWCAG 2.1のレベルAAへの適合を目指し、試験を実施してその結果を一般に公開しています。
——実際に「Graffer スマート申請」を利用した市民からはどのような声がありましたか。
例えば、視覚に障害のある利用者の方からは「ボイスオーバーを使用して目に障害があっても一人で登録できました」などの声をいただいています。これまで困難だった手続きがスムーズに行えるようになったことが評価されている様子がうかがえます。

障害を持つ利用者からポジティブな声が届いている。
ウェブアクセシビリティ担当チームの想い
——今回の認定では、組織体制についても評価されています。実際にアクセシビリティを担当しているメンバーはどんな人たちなのでしょうか。日ごろどんな想いでアクセシビリティに取り組んでいるのか聞かせてください。

アクセシビリティに関する当事者へのインタビューを行った際の様子
松倉さん
デザインエンジニアチームの一員として、障害を持つ方を含め、すべての人が迷うことなく安心して操作できるサービスを届けたいという想いを持って、設計・開発に取り組んでいます。グラファーに参画するまでは、アクセシビリティを意識した開発に本格的に取り組んだ経験はありませんでした。当初実装したものも、アクセシビリティの観点が不足しており、いただいた指摘をもとに修正を重ねる中で、その重要性を深く実感しました。具体的な経験を積む中で、単に「動く」だけでなく「使いやすい」サービスを目指すことの重要性を実感し、視覚障害者を含む多様なユーザーに寄り添った設計を心がけるようになりました。現在は、視覚障害者の視点に焦点を当てた開発に取り組むことが多いですが、それにとどまらず、身体が不自由な方や高齢者など、多様なニーズに応えられるサービスを届けるため開発を進めていきたいと考えています。
下瀬さん
以前、視覚に不自由のある方が「スタッフが足りていないので対応できない」と言われ、困っている様子を目にしました。この経験から、オンラインサービスにおいても、「キーボードで操作をしていた際に、意図しない場所へ移動して操作が分からなくなってしまう」「画面上の文字情報を認識できない」というような問題が起きないように考慮しながら開発に取り組んでいます。グラファーではアクセシビリティに対する取り組みを公表していますが、こうした公表が社会全体のアクセシビリティへの関心を高めるきっかけとなれば嬉しいです。
堤さん
アクセシビリティというと、障害がある方だけに関係するものだと思われるかもしれません。しかし実際には、誰にとっても必要になる可能性があるものです。生まれながらの障害だけでなく、さまざまな段階や状況で一時的または永続的に機能制限を経験することがあります。例えば、事故によって一時的に体が思うように動かなくなることや、加齢によって視力が低下したり聴力が落ちたりするタイミングは、誰にでも起こり得ることです。また、怪我や病気による一過性の不自由さも考えられます。もし自分自身や大切な人がこうした状況に直面したときに、「このサービスがあって助かった」と思えるような存在でありたい。その想いを胸に、一歩一歩着実に開発を進めています。
——今後はどのようなことに取り組んでいきますか。
これからも、アクセシビリティに対する取り組みをさらに深め、より多くの方にとって使いやすいサービスを目指していきます。利用者の声を通じて、まだ十分に対応できていない課題も見えてきています。これらの声に真摯に向き合い、一つひとつ解決していくことによって、「Graffer スマート申請」のアクセシビリティを、維持するだけでなく、さらに高いレベルへと引き上げていきたいと考えています。
また、「Graffer スマート申請」以外のプロダクトについても、アクセシビリティを確保するための取り組みを進めていきます。あわせて、障害を持つ当事者の方々へのインタビューを積極的に実施し、現場の声を直接聞くことで、よりリアルなニーズを反映したサービス開発を行っていきたいと思います。
誰もが豊かに暮らせる未来を作るために機能するプラットフォーム作りを目指し、すべての人が自分らしく、生きる上での壁を感じることなくサービスを利用できる社会を実現するために取り組んでいきます。
グラファー Govtech Trends編集部
Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。
株式会社グラファー
Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。